
痛みの中、何度も果て…
「粗相をしたことがカンに触ったのか、翌日は水仕事を命じられました」
この日は、配膳の仕方を間違ったことが、川口の逆鱗に触れた。脇腹を抓られた彼女は、咄嗟に玄関に踵を返していた。そのときだ。何者かが廊下をやって来る。川口の父親だった。
訴え掛けようにも、歯の根が合わない。川口の父親はそんな彼女を支え、一歩ずつ歩かせた。だが、何かが変だった。彼女は、座敷牢の方向へ運ばれていたのだ。
川口の屈強な腕で平田さんは牢の中へねじ込まれ、尻を蹴り飛ばされた。そして、身体を海老のように反らされ、天井の梁から縄で吊された。
「川口の父親は、目を逸らして去って行きました。両親は完全に言いなりだったのです。食事時に喋らなかったのも、ちょっとした失言で川口が爆発することを畏れていたからなのです」
手首の肉に縄が食い込み、身を捩れば捩るほど更に深く食い込んでくる。5分もたたぬうち、平田さんは、裂けるような手首の痛みに悲鳴をあげた。川口の手が、無情にも腿の間を分け入って来る。
――コイツ濡れてやがる!
容赦ない指の動きに、秘汁がボタボタといやらしい音をたてて落ちた。
川口は棒を振り上げると、平田さんの尻を打ち据える。激痛と共に突き抜けるような快感が沸き起こっていた。赤く膨らんだ乳房を川口がひねる。平田さんは絶頂に達していた。
川口は、彼女の耳元で囁いたという。
――俺は江戸時代から続く拷問人家系の末裔だ。逃げられると思うなよ。
奇妙なことに、川口は機嫌が良いと、平田さんを買い物などで外に連れ出した。
ある日、幹線道路沿いのショッピングモールに赴いたとき、彼女は手洗いに立った。
逃げるつもりはなかった。その時、平田さんは、自分の意思で動こうとすると、脳裏に川口の怒声が聞こえるまでになっていたのだ。
「用を足した後、私は鏡に写った自分の顔を、久しぶりに陽の光の中で見ました。そこには頬がこけ、目ばかりがギラついた自分がいました」
平田さんは、言いようのない嫌悪感に襲われた。次の瞬間、彼女は換気用の窓によじ登っていた。そして、裏のロータリーで駅へ向かう無料循環バスに飛び乗った。
駅前の交番で電話を借りた彼女は、友人の車で東京に戻ることが出来たという。
「会社には川口から何度も電話があったため、怖くなって退職届を出しました。そして、弁護士さんに相談したのです」
東京で母親と折り合いが悪かったこともあり、実家を教えていなかったのが幸いだった。
友人宅に身を寄せ、訴訟に備えたが、川口は深追いして来なかったという。今は関西で幸せな家庭を築いているという平田さんの穏やかな横顔に、過去を偲ばせる影はない。
彼女は最後にこう言った。
「弁護士さんから、前の奥さんの写真を見せられたとき、手足が妖しい疼きでじっとり汗ばんできました。何故なら、私の背中にも、沢山の赤黒い蛇がのたうっていたからです」
それにしても、川口の言う拷問の家系とは一体何であろうか。
かつて、地方の陣屋敷では、司法による拷問が日常茶飯事に行われていたというが、それを執り行った闇の一族が存在したというのだろうか。
それとも、単に呪われた血が口走らせた妄言だったのであろうか。
平田さんの傷は、今も消えることはない。(井戸高)
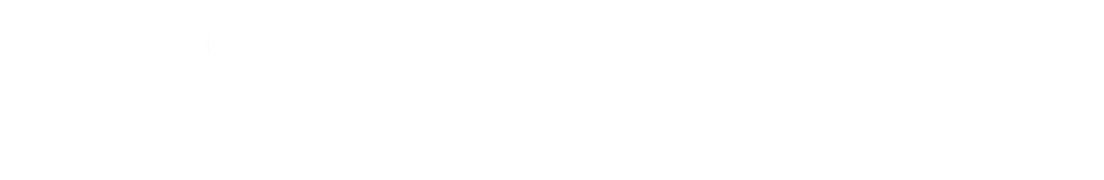
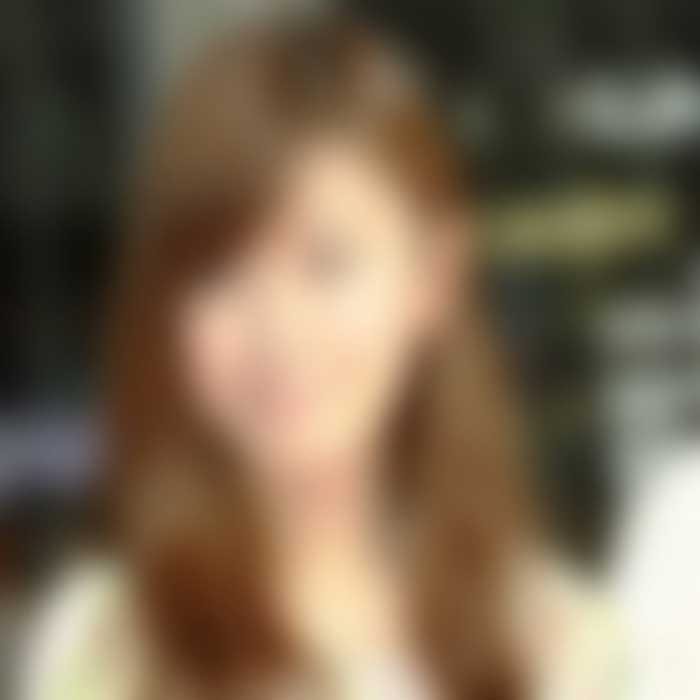
















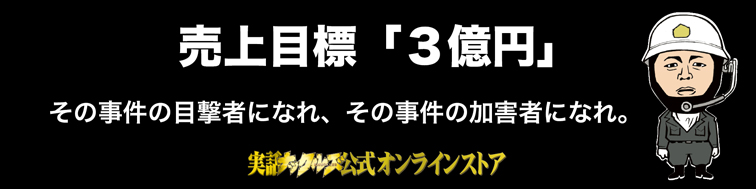

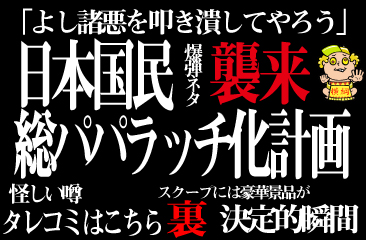
Leave a Reply