
写真はイメージ
来る日も来る日も繰り返される淫肉折檻
婚約者の闇の顔
雪のように白い女の背中だった。しかし、透き通るようなその肌には、おびただしい火膨れのような傷痕が、折り重なっていた。無数の蛇のように、ぬめりを帯びてのたくっている。
「その写真は、あの男の別れた奥さんが、以前訴訟を起こしたとき裁判所に提出したものでした」
平田香織さん(仮名・現在40歳)は震える声で話す。弁護士は、写真を手渡して言ったという。
――もう少し逃げ出すのが遅かったら、あなたもこうなっていたかもしれません。
※
10年前の春、東京の勤め先で任された案件をまとめるため、北関東X県に不定期で通うことになった平田さんは、現地の取引先を交えた飲み会で、川口(仮名)というスポーツジムのインストラクターに出会った。精悍な肢体に魅かれなかったと言えば嘘になる。しかしそれ以上に心を動かされたのは、川口の柔和な人柄だった。
「40過ぎで、バツイチ。でも全然気にならなかった。それなりに女性と接する職場にいながら、女の影が全くないのが不思議でした」
と彼女は話す。関係が深まるまで、時間はかからなかった。
「今思うと、後輩が次々結婚していく中、焦っていたかもしれない。プロポーズを受け止めたのも自然な流れでした」
その年の7月、平田さんは一週間の休暇を取り、川口と共に駅から車で30分ほどの山合いの町を訪れた。町を見晴らす山裾に、彼の実家はあった。
居間に三社の社を祀った神棚のある大きな屋敷だった。
その夜は、浅黒く日焼けした川口の両親が、手料理と地酒でもてなしてくれた。両親共、極端に口数が少ないことを、平田さんは奇異に感じたという。
「川口が私のことを紹介しても、上目遣いでうっすらと笑うだけです。かと思うと腫れ物にでも触るように、二人共私のことを気遣ったりする。釈然としないものを感じました」
事態が異様な様相を呈し始めたのは、翌日からだった…
「きっかけは『神棚の“供え物”を裏山で採って来てくれませんか』と、片脚の不自由な川口の母親から頼まれたことでした」
採って来た榊(さかき)を手渡した途端、川口の母親が魚のような目で見返したのを、今でも覚えている。夕食の前、奥の間から川口の呼ぶ声がした。廊下の先で、襖の隙間から蝋燭の明かりが漏れている。その向こうから川口の太い手が、彼女の掌を掴んで引き寄せた。
「私は悲鳴を上げました。二十畳程の居間に、木格子の檻が作られていたんです」
そこは座敷牢だった。格子には、大小様々な笞や青竹といった打擲具、荒縄、足枷などの拘束具が掛けられ、蝋燭の光の中で揺れている。
川口は、布で巻かれた棒を手に取った。平田さんの背筋は凍った。そこには、血痕のような斑文が幾つも染み付いていたのだ。
へたりこむ平田さんの服を川口は容赦なく脱がせ、縄で手首をきつく縛り上げた。
「川口は、私が昼間、母親に供え物を言いつかった折り、榊と間違えて、仏壇用の樒(しきみ)を採って来たと言って叱り付けました」
川口が数を数えながら何十回と打擲する。平田さんは、失禁した。その瞬間頭が真っ白になり、果てたという。
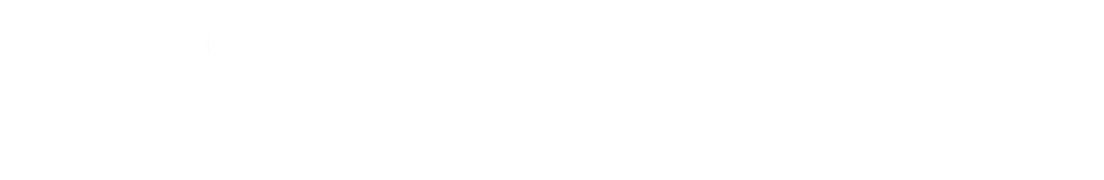
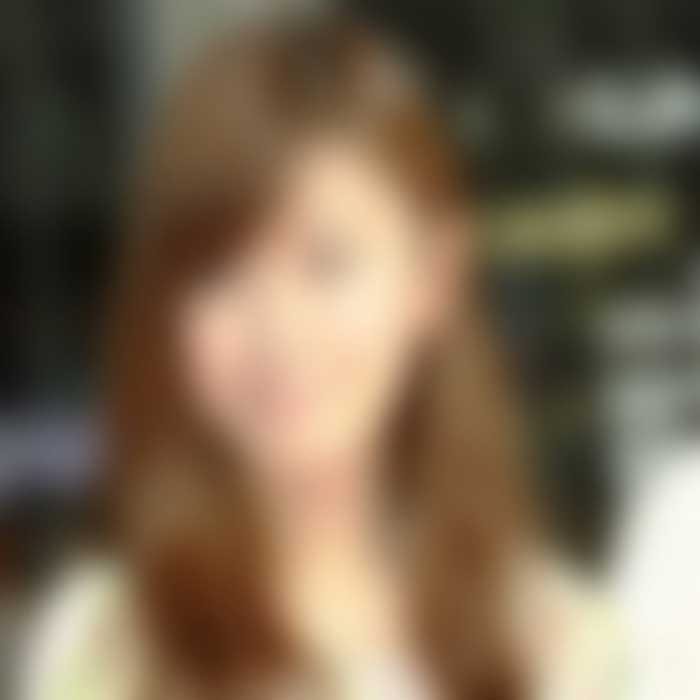
















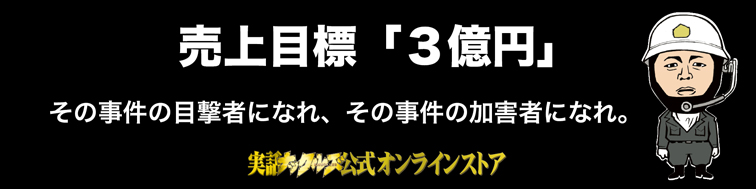

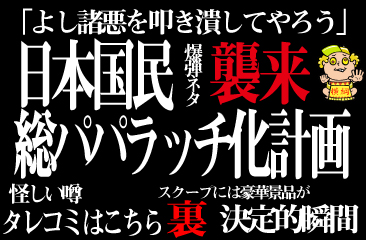
Leave a Reply